日本は長年にわたって少子化の進行に直面しており、出生率は低下の一途をたどっています。このままでは、将来的に労働力不足や社会保障の維持が困難になることが懸念されています。
しかし、みなさまご存じの通り従来の少子化対策、例えば男女共同参画政策や子育て支援等では、根本的な問題解決には至っていません。

マジで、日本はどうなっちまうんだ。。、

ただ、実現できるかどうかは不明だが、幾つかの観点で少子化解決の糸口になりそうな研究をいくつか発見した。
今のまま少子化が進行してしまうと、社会保障は肥大し高齢者福祉を維持するために何もかも奪われる地獄になるでしょう。
私は人口学の専門家ではありません。
しかし、学術論文を読み漁るといくつかの研究で、少子化対策として効果が期待できる施策の方向性はある程度分かってきています。現実のデータや研究成果を参考に、結婚率や出生率を高めるための戦略を考察していきます。

なお、本稿で提案する施策の中には、現代の一般的な倫理観や価値観を捨てざるを得ないものも含まれています。そのため、議論を読む際には、あくまで「少子化を改善するための効果的な手段の一例」として理解していただきたいと思います。

大丈夫???笑

だからこそ、少子化を解決する方法を発見した国家が存在しないのかもしれないがな。
本稿では、男女政策の見直し、教育改革、都市計画・税制の工夫といった具体的な施策を順を追って紹介していきます。
個人の選択を尊重しつつも、社会全体として出生率を改善するための総合的なアプローチを示すことを目的としています。
読者の皆様には、現代社会における少子化の構造的課題と、それに対する現実的な施策の方向性を理解していただければ幸いです。
この記事を書いた人 この記事の対象読者と結論
イントロが少し長くなりましたが、ここで改めて 自己紹介をさせてください。


はじめまして。「論文解説お兄さん」を自称している、Murasaki(むらさき)だ。

友人兼水先案内人のニートです!
はじめまして。この記事を書きました Murasakiと申します。
論文を用いて、少しでも人生が明るくなるようなお手伝いをする情報発信をしています。
マルボロの赤を愛煙する喫煙者です。
詳細につきましては、以下の記事をご確認ください。
このブログでは、ほとんどの場合論文の引用や信頼できる公的機関等が発表した統計データの一次情報を引用して、一貫した主張を展開するスタイルを徹底しています。
ちまたに流れる「お気持ち表明」的な三流ハウツーとは一線を画した内容になっていると思います。
また、サブスクリプションもはじめました。毎月「コーヒー1杯くらいなら奢ってやるか」といった優しい方向けです。
ぜひ、ご支援いただけると幸いです🥺
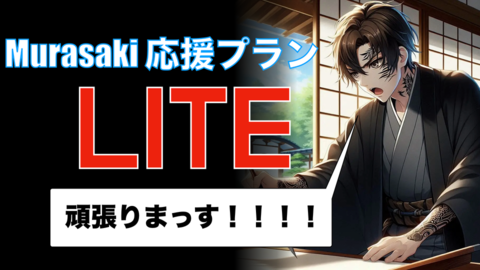
この記事は以下のような読者を想定して書きました。
この記事は長いので、先に結論も述べておこうと思います。
ここからは、実際に学術論文や統計データを紹介しながら、少子化対策に有効と思われるアクションを紹介していきます。
男女共同参画の廃止──結婚率を上げるために
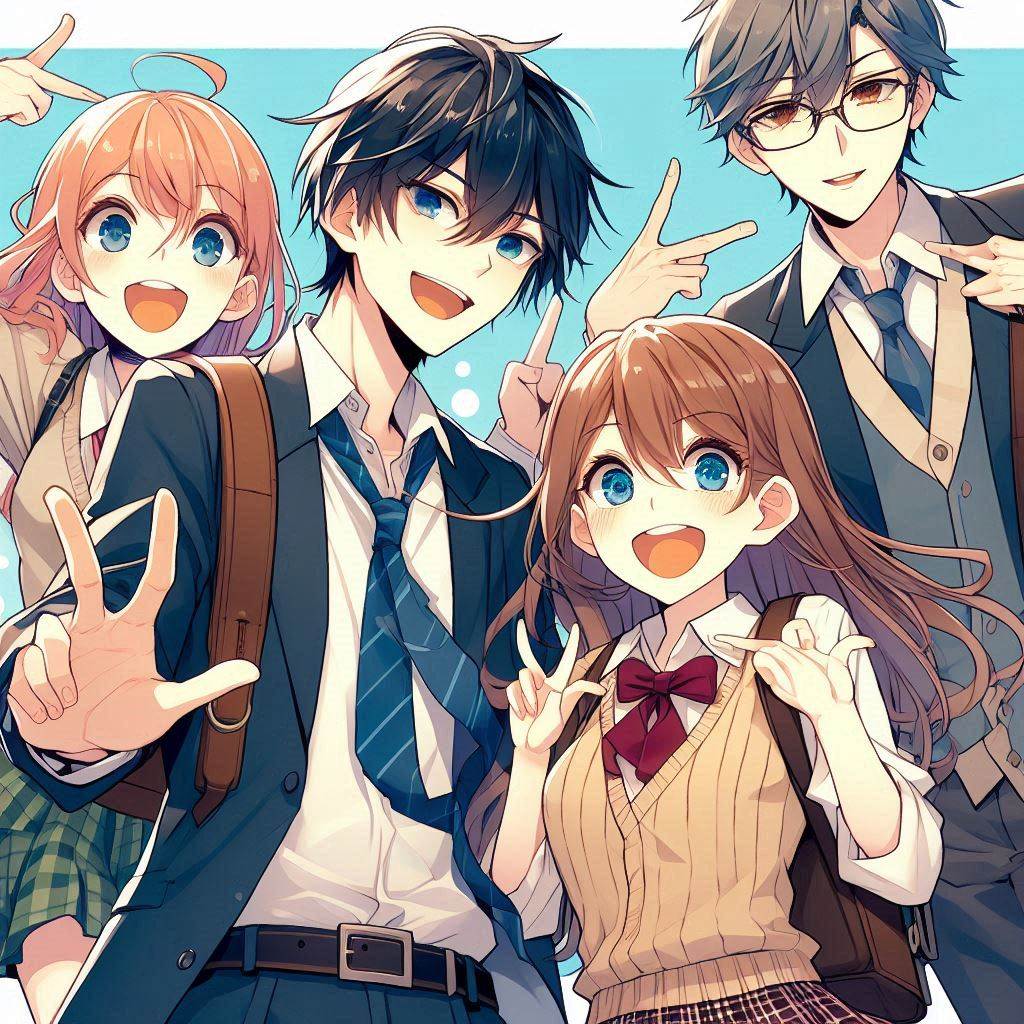
これまで日本では、男女共同参画の名の下 さまざまな女性優遇策をとってきました。
そこには高額な税金も投入され、そろそろ「男女共同参画の推進は意味があったのか?」をまじめに検証する時期に入ってきたと言えるでしょう。
ご存じの通り、男女共同参画によって女性を優遇する措置を取り続けてきたのに少子化は加速しています。果たして、本当にこの施策に意味はあったのでしょうか?
女性の大学進学は制限すべき
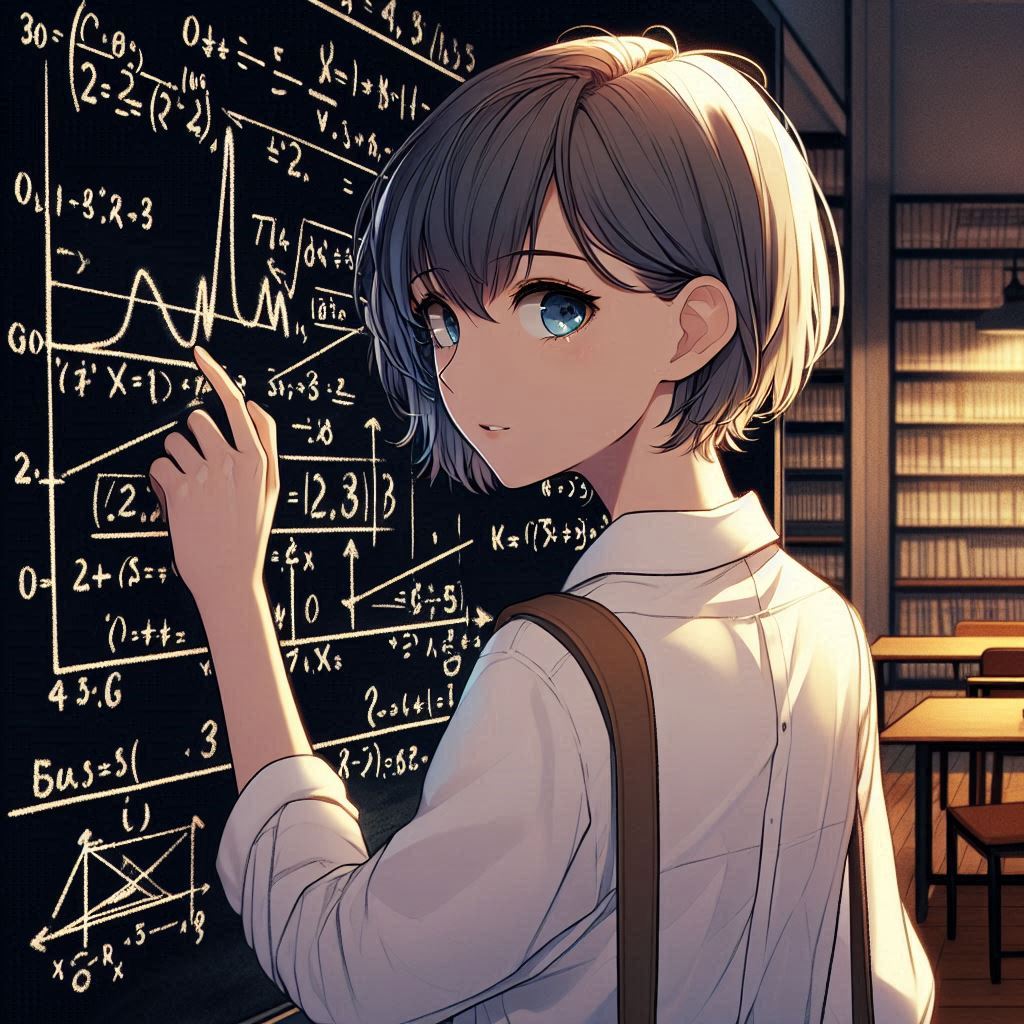
まず結論を述べます。少子化を改善するためには、専門職を除き、女性の大学進学は制限するべきです。

うわぁ。。、各方面から怒られるやつ…

ちゃんとその理由もあるから、私を燃やす前に話だけ聞いてくれよな笑
こんなこと言ったら各方面から怒られそうですが、そんなの知るか。
ここから先は、権威ある医学雑誌The Lancetにて公開された学術論文をベースにグロテスクな真実をお伝えしていこうと思います。
「こども家庭庁」が必死に子供を育てるための関連法案に予算をつけていますが、はっきり言ってこんなの全部ゴミです。金の無駄です。
ここから先は、The Lancetに掲載された論文を含む5本の論文と5本の公的データを用いて全てを解説します。
ここから先を読めば、あなたは真の少子化対策に到達することでしょう。
ここから先は、過激な内容を連発していきますので、ペイウォールで仕切らせていただきます。
記事単品だと¥1,000~で購入できるようにしていますが、サブスクリプションに加入すれば半額の¥500で読めるようにしておきます。
サブスクリプションなら、これ以外の有料記事も読めるのでおすすめです!





コメント
この少子化対策には3点問題点があるかと思います。
1点目は憲法第二十三条に書かれている学問の自由に反しているという点です。
2点目は女性が10代、20代前半で結婚出産する場合、パートナーとなる男性も同世代が大半になることが想定されますが、学生や新入社員の身の上で3人分の家計を支えるのは厳しいのではないかという点です。
3点目は女性を大学から締め出したところで現在の経済状況を考えると単純に働きに出る年齢が下がるだけではないかという点です。
個人的な考えとして子育てにはお金がかかるという認識が一般化し、結婚しても子どもを産まない家庭もある中で単純に女性の活動範囲を制限するだけでは少子化改善は難しいのではないかと考えます。
この記事でも追記しますが、医学雑誌『The Lancet』に掲載された204カ国・地域を対象とした包括的な人口動態分析では、合計特殊出生率低下の主要な駆動要因が経済的貧困ではなく「女性の教育水準の向上」と「避妊へのアクセスの改善」であると実証されました。
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(24)00550-6/fulltext
この記事でも主張していますが、学問の自由とやらは確かに考慮すべき観点であるものの「それらを度外視した方法でしか、少子化は解決し得ないのでは?」と思っています。
どうせ大学行っても、そこで学んだことなんて使わないんですし笑
少子化対策は統一教会の集団結婚式を公認するのが一番良いと考えます。高額献金にしても、建前だけでも人類愛を説いて下さるから。少なくとも個人の私欲だけで婚活界隈を疑心暗鬼にした「頂き女子りりちゃん」よりはマシ。更に言えば被害者が罵倒される鬼畜ぶりも。職業訓練なら一般企業主導で、人格とか人間力とか人類愛ということなら統一教会で。統一教会を礼賛するわけでは無いが、少なくとも頂き女子りりちゃんの鬼畜ぶりと比較すれば、頂き女子韓鶴子ちゃんの人類愛が理解できるはずだ。
氷河期再雇用のための図書館司書ワークシェアリングってどうですか。図書館司書は誰でも出来るラクな業務なので、最低賃金未満の時給700円でかつ週一回三時間から出勤可能にできます。大阪維新が図書館司書を非正規化しても利用者から文句は出なかったので、その延長としてのダンピング化です。