北九州市で「学校給食をハラル対応に」という陳情が出され、それがSNSで大炎上しています。

つまり…???

イスラム教徒は、ハラル食(豚、アルコール禁止)だから 日本の学校でも配慮してくださいってことだ。
「給食くらい配慮してもいいのでは?」――そう思う人もいるかもしれません。
しかし、その“小さな譲歩”はやがて取り返しのつかない大きな問題へと連鎖していく可能性があります。
これはヨーロッパがすでに経験してきた現実であり、スライディング・スケールによる文化侵食の典型例です。
果たして、日本は同じ道をたどるべきなのでしょうか。
この記事では、なぜ学校給食のハラル対応を断固として認めてはならないか 解説します。
この記事の著者 / この記事の結論


はじめまして。「論文解説お兄さん」を自称している、Murasaki(むらさき)だ。

友人兼水先案内人のニートです!
はじめまして。この記事を書きました Murasakiと申します。
論文を用いて、少しでも人生が明るくなるようなお手伝いをする情報発信をしています。
マルボロの赤を愛煙する喫煙者です。
詳細につきましては、以下の記事をご確認ください。
このブログでは、ほとんどの場合論文の引用や信頼できる公的機関等が発表した統計データの一次情報を引用して、一貫した主張を展開するスタイルを徹底しています。
ちまたに流れる「お気持ち表明」的な三流ハウツーとは一線を画した内容になっていると思います。
また、サブスクリプションもはじめました。毎月「コーヒー1杯くらいなら奢ってやるか」といった優しい方向けです。
ぜひ、ご支援いただけると幸いです🥺
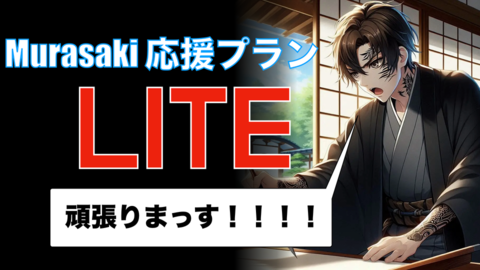
先にこの記事の結論を述べる前に、一点注意事項があります。
それは、イスラム教の文化を否定している訳ではないということです。

私は、自分の友人の多様性の高さには大変自信があります。
外資コンサルで年収1,500万overのやつもいれば、ハプバー狂いのビッチ、女遊びするために東京に来た限界研修医、障害者手帳2級保持者…
当然その中には、さまざまな国籍の方もいますし、いわんやムスリムも存在します。
私は彼らのことが大好きですし、彼らも私を大事にしてくれます。当然文化の違いもありますが、お互いリスペクトを持って、その違いも許容し 適当に楽しくやっています。
繰り返しますが、それは互いに対するリスペクトがあるから成立するのであって、それを感じなかったら人間関係は破綻するでしょう。
今回の記事は、ハラル食の文化は別に否定するつもりはないし勝手にやってくれればいいと思っているが、それを行政に要求するのはやりすぎだし リスペクトを欠いているんじゃない?程度の話です。

なんでそんな当たり前のこと言ってんの?

どこの誰とは言わないが、「多文化共生!」「xxxに配慮しろ!」「差別を許さない!」系の人たちに怒られたくないからだ。
さて、注意はこのくらいにして この記事の結論を述べます。
繰り返しますが、私がムスリムの友人と仲良くやっているのは 彼から日本文化に対するリスペクトを感じるからです。
そして、彼もまた 私がイスラム教の文化に対してリスペクトを持っていると感じているから、問題なく接しているのでしょう。
彼の作った、謎のハーブが大量に入ったエスニック料理、最高に美味かったです。
それでは、本題に入っていきましょう〜〜〜!
北九州市に提出された、ハラル給食に関する陳情
学校給食は、戦後の日本で「子どもたちに平等に栄養を与える」ことを目的として始まりました。
同じメニューをみんなで食べることは、単なる栄養補給ではなく、食育や共同体験の一部として大切にされてきました。
ところが近年、イスラム教徒家庭から「学校給食をハラル対応にしてほしい」という声が上がっています。
実際、北九州市では保護者による陳情が行われ、静岡市では豚肉やアルコール由来の調味料を排除した「スマイル給食」がすでに導入されています。
これがSNS上で大炎上し、大きな議論が巻き起こる結果となりました。
これに対して、真っ向から反論しているのは 北九州市議の井上じゅんこ氏です。

まぁ、保護者の気持ちも理解できるけどな。

すまんが、私は1mmも理解できなかった。
一見すると、「子どもたちが安心して食べられるようにしてあげるだけのこと」に見えるかもしれません。
しかし、ここで問題になるのは 「学校給食は特定の宗教に合わせるべきか?」 という根本的な問いです。
ここからは、なぜムスリム対応の給食をすべきではないのか 考えていきたいと思います。
そもそも、ムスリムに合わせた食事を 関係ない日本人に強制するのは意味不明
まず大前提ですが、給食はその地域の小中学生全員が食べるものです。仮にムスリム対応のハラル給食になった場合、日本人全員がその給食を食べることを強制される訳です。
確かに、安心して少しでも多くの児童・生徒が給食を食べれるように配慮するのは当然必要なことです。そして、ムスリムが少数派だから「一切配慮しない」というのも、私は間違っていると思います。
…ですが、少数派にいちいち配慮していたら どんな問題が起こるのでしょうか???

え、、、どうなるんだろ。

果たして、配慮ってのは何パターンあるんだ???
確かに配慮は大切です。
しかし「xxxアレルギー」「お魚はニガテだから食べられない」「イスラム教徒だから、豚はダメ」… と全パターンに配慮していたらどうなるでしょうか。
当然、給食の準備なんてできっこないでしょう。
実際北九州市では、アレルギー児童2,500人存在するのに対して、1,000人が自分の弁当を持ってきています。個別最適で給食など出せるわけがないからです。
…にもかかわらず、ムスリムには配慮しろというのは、リスペクトに欠いた行動だと私は思います。

陳情出した保護者が、アレルギー持ちの児童は弁当を持ってきているという現状を知らなかっただけかもしれない。とはいえ、日本人全員合わせろというのは、リスペクトのかけらもないと思う。
陳情を出した保護者の背景を全て理解することはできません。
ですが、日本人ではない上、勝手に日本を選んで来ている訳ですから、日本の文化を尊重するのは当たり前です。
にもかかわらず、勝手にやってきた側の人間が「私たちの文化に合わせろ」と要求してくるのは、流石にリスペクトのかけらもないと思います。
「それはイスラム教を差別してる!!」系の意見に対する反論
この手の「多文化共生」と言っている人たちの中には、一度反論すると「差別だ!」と、ピーピー文句を言ってくる人がいます。
「差別だ権利だ宗教弾圧だ!!!!」と喚く界隈の人たちには、どのような反論をすれば良いでしょうか。

いるね。こうゆう人たち。

反転可能性テストを課せばいいと思う。
…多分、これで一撃だと思います。
すなわち「日本の食文化には豚や醤油(製造過程でアルコールが発生する)が当たり前に根付いている。それを拒否して、自分の文化を押し付けてくるのは 明確な日本文化差別ではないのか?」
単なる「ハラル給食問題」だけでは済まないかもしれない
さて、これまで北九州市の個別の事象を主題に取り上げて
と反論してきました。
ですが、この問題は単なる北九州市だけの問題に留まらず 日本全体の問題だと強く危機感を持つべきだと私は思います。
ここからは、なぜこの「北九州市のハラル給食問題」が日本人全体の問題なのか?をまじめに考察していこうと思います。
スライディング・スケール論法 ― 小さな譲歩が大きな文化侵食へ
前の章で、北九州市の個別の事例を取り上げて「イスラム教徒のハラル給食に関する要求を一歳受けてはならない」と述べました。
この記事を読んでくださった多くの方が、賛同してくれる… と期待しております。

この記事を読んだ人はそうなのかもしれないけど、他の人はどうだろうね。

ここから先は、その危険性をまじめに考察しよう。
「給食くらい配慮してもいいのでは?」
――そうした“小さな譲歩”をついついやってしまう人も多いかもしれません。
ましてや、イスラム圏の方々が日本で増えてきて可視化されるようになってきたのはコロナ禍以降の話なので、この手の移民や外国人問題に対して明確な意見を持っていない方も多いのではないでしょうか。
ここからは、外国人の小さな要求を「まぁそれくらいいいのでは?」としてしまうことで生じるリスクを考えようと思います。
スライディング・スケール論法
「ハラル食の給食くらい、認めてもいいんじゃない?」
という小さな要求から始まるのが、スライディング・スケール論法です。
最初は一見、ささやかな要求です。
しかしそれが認められると、次はこうなるのは目に見えています。
- 「北九州市ではハラル給食なんだから、うちの自治体でもハラル給食にしろ」
- 「礼拝のために公園や道路を使わせろ」
- 「土葬を認めろ」
- 「公共施設に礼拝の場所を作れ」
- 「シャーリア法を一部でも反映させろ」

あれ?これって、結構まずいんじゃない?

マズいなんてもんじゃない。
確かに「小さな要求だし、日本人も豚以外でタンパク質を摂取すれば問題ない」という意見も理解できます。
しかし問題なのは、一度認めてしまうとそれがムスリムにとっての成功体験になり、次から次へと要求が出てくるようになることです。
北九州市でハラル給食だったんだから、うちの自治体でも出してくれよ という意見は当然出てくるでしょう。
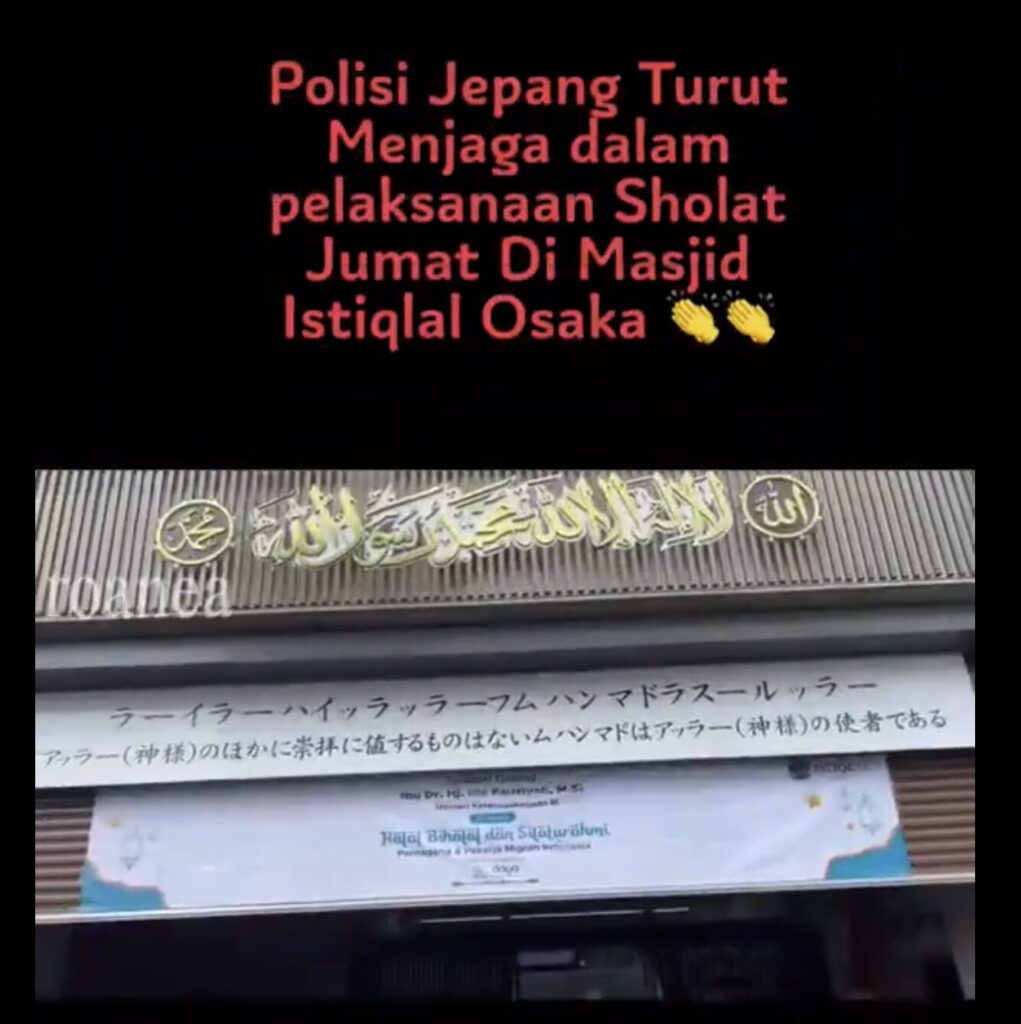
こうした段階的拡大は、ヨーロッパで現実に起こってきたことです。
「少数派への配慮」が「多数派への制度変更」にまで発展し、社会の摩擦や分断を生んでいます。
とくに、路上で通行を妨げてでも礼拝をしたり、土葬を要求したりする行為は、日本の文化に対するリスペクトを欠いているばかりか、他国の人間が現地の人間に「自分達の文化に合わせろ」という行為です。
そして彼らを批判したら、被害者ヅラ全開で「人権侵害だ」「宗教弾圧だ」と繰り返し反論してくるでしょう。

地獄絵図w

日本は幸い、周囲を海に囲まれた島国だ。
欧州で起こった過程にタイムラグがあるはずだから、早く気づいて対処するべきだ。
つまり、一度「小さな特例」を認めてしまえば、それを前例として「次の要求」がやってくるのです。
これこそが スライディング・スケールによる文化的侵食 であり、日本社会が直面しつつある最大のリスクなのです。
だからこそ、ハラル給食のような“入口”の時点で、きっぱり線引きをするべきなのです。
ヨーロッパの事例
「スライディング・スケール」が現実にどう進んでいくのか、その典型がヨーロッパです。
フランス、ドイツ、イギリスなどでは、移民・イスラム教徒の増加に合わせて最初は小さな配慮が行われました。ハラル食品を学校や公共機関で選べるようにしたり、礼拝スペースを一部の公共施設に設けたりする取り組みです。
ところが、そうした譲歩はやがて次の段階に発展しました。

次の段階とは、やはり。。、

まぁ、その辺りは察しの通りだ。
結果として、「多文化共生」が「文化的分断」に変わり、地域社会の緊張や対立を深めています。特にフランスでは、公共の中立性を守る「ライシテ(政教分離)」の原則と移民への宗教配慮が正面衝突し、大きな社会問題となっています。
イギリスでは、これらの移民問題に対して問題意識を持った英国人が立ち上がり、大規模なデモに発展しました。
スウェーデンでは、移民推進はだった左派政権が倒れ、右派政権が「移民は500万円あげるから、お願いだから帰って」という政策を打ち出しています。

うわぁ。。、ひでぇな。

国境を海で閉ざされた日本も、真剣にこの問題に向き合わないと大変なことになるかもな。
日本はまだ移民国家ではありません。しかし、すでに北九州市や静岡市での「ハラル給食」のような事例が現れ始めています。
ヨーロッパの“失敗例”を教訓とし、同じ道をたどらない姿勢を明確にする必要があるのです。
さいごに
これまで、北九州市のハラル給食を例に挙げ
「断固としてこのようなものを認めてはならず、日本に帰化することを強く要求するべきだ」
と述べてきました。
そして、小さい譲歩であっても、それをフックに要求がエスカレートし 手に追えなくなる未来を、ヨーロッパの実情を交えて紹介しました。

ちゃんと、ニュースを読んで自分の意見を言えるようにならないとね。

その通りだ。そして、理性的な観点で議論できるようでなければならないな。
これまで、外国人問題を中心に扱ってきましたが、これは次の問題と表裏一体です。
すなわち社会保障と女性問題です。
日本は少子高齢化に突入し、今後は「戦略的撤退を行ないつつ、数百年スケールで人口を安定させていくフェーズ」に入って行きます。
当然、若い人が減るのだから 支えられる側の人間が多くなることが確実な日本では、社会保障を大真面目に議論しなければなりません。
2025年の社会保障を今後も維持していく方法は、以下の2つです。

絶対無理じゃん

その通りだ。
介護施設の労働を見たことがある人はわかると思いますが、誤解を恐れずに言い切れば、まともな学歴を有している人は誰もやりたくない業務ばかりです。(本当に、言い方きついのは百も承知ですが、他人の高齢者のきったないウンコを低賃金で拭く業務 本当に心の底からやりたいんですか?)
2025年の社会保障を維持したければ、マトモな学歴を有していない外国人の労働力に頼るしかないのです。
そして、社会保障の問題は男女論… ひいては女性問題と表裏一体であることを知っておくべきです。
なぜなら、女性は既婚独身に限らず 男性より長生きで、しかも独身男性が亡くなる年齢のピークは65歳前後だからです。
…となると、社会保障を食い潰している最大ボリュームは女性であり、彼女たちの
「私たちは、可哀想な被害者🥺」
に永久に付き合っていたら、社会保障は大変なことになるし、多くの(低品質な)外国人の労働力に頼らざるを得ないでしょう。
一見関係なさそうな外国人問題が、実は日本の特大イシューである社会保障改革と男女論と表裏一体であることを述べて、この記事を終わろうと思います。






コメント